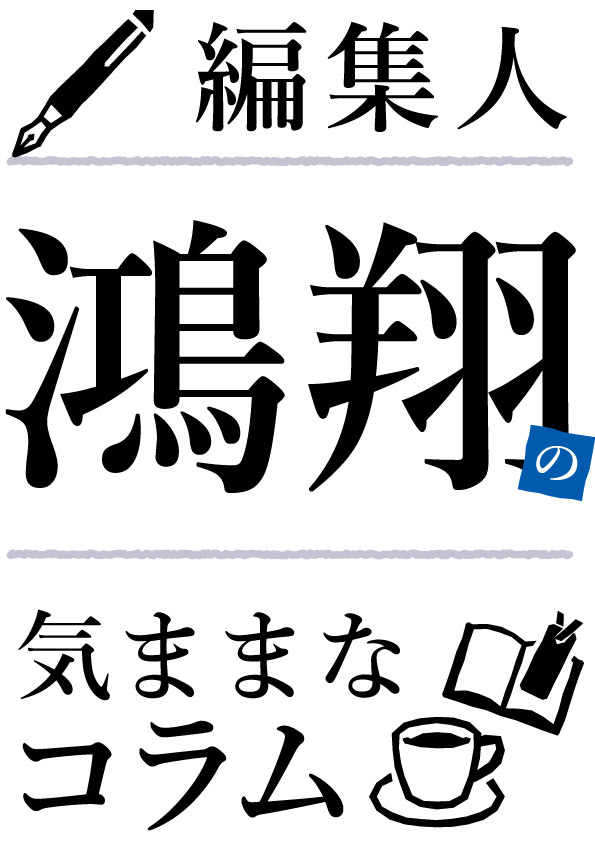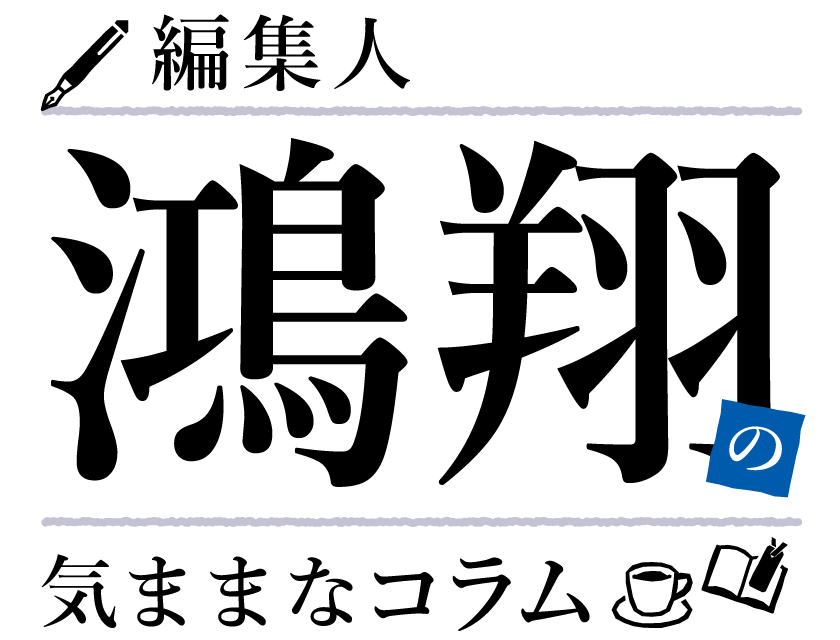年収上昇と企業業績
2024年08月31日
本年7月の日本経済新聞の1面に、「年収1,000万円の先に深化の扉」と題した記事が掲載されていました。東証プライム上場企業(金融を除く約1千社)の平均年収と業績の関連性について、アメリカの大手企業課長職の平均年収が22.5万ドル(円換算で約3,600万円、米マーサー社調べ)であることを引き合いに出し、日本国内で平均年収が850~1,000万円未満の企業では年収を上げるほど業績が伸びる傾向にあったとされています。しかし、日本企業全体では年収500~550万円が所得の中心値であることを鑑みると一部の大企業に所属する従業員を対象とした数値であり、あくまでも限定的側面があります。人的資源への投資が重要だとされる最近の風潮からしても、物価・為替等を考慮すれば今後数年先まで年間3~5%の賃金底上げを続けられる企業はごく一部に限られるでしょう。
記事には、以前ご紹介したキーエンス社(平均年収2,200万円)にも触れていましたが、業績連動型給与体系(年4回の賞与支給額が年収の半分以上を占める)の良い部分として「部署の業績が報酬に直結するため、成果の出ていない同僚を周囲の従業員が手厚くサポートしていること」、「業績連動式が経営参加意識に繋がることを」を挙げています。ただ、少し斜め目線で見た場合、中途を含む新規入社従業員のスキルレベルが元々相当高いであろうことが推測され、現在問題視されている人手不足への対応に苦慮する他企業(特に中小企業)にとっては夢のような採用母集団だとも言えるでしょう。また、海外の投資会社も内部留保還元型企業から人的資源型企業に投資の軸足を移しつつあると聞きます。
もし、日本で企業に勤める従業員の年収が平均1,000万円を超えると仮定したならば、競争力に劣る企業は淘汰され、個人経営店は廃業等を余儀なくされることになるのか編集人には想像がつきません。それよりも、国力の源泉である人材育成と頭脳の流出に税金を優先的に廻せるような改革を進めることが先決のように思います。